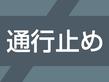「毎日ショパンばかり聴いていたら飽きるでしょ」。10月の約1カ月にわたってショパン国際ピアノ・コンクールの動向を追いかけてきたが、時にそのような言葉を投げかけられることもあった。確かに、当初は筆者も「つらいかもな」と思っていたのだが、聴き続けているうちに、飽きるどころかむしろ作品やショパンへの愛が強まり、コンクールが終わってもショパンの音楽なしには生きていけない体となってしまった。(取材・写真・文 共同通信=田北明大)
▽さまざまなショパン
出場者らの演奏を聴きながら、さまざまなショパンの姿を想像した。2位のケヴィン・チェンが2次予選で弾いた「12のエチュード 作品10」全曲の、技巧の難しさを忘れさせてくれる華麗で流れるような演奏からは、繊細なだけではなく才能を遺憾なく発揮して人々を魅了しようと意欲みなぎる若きショパンの姿が浮かんだ。3位のワン・ズートンが3次予選でピアノ・ソナタ第2番「葬送」の後に披露した「ワルツ ホ長調」では、優しさに満ち、生きていて良かったと思わせてくれる温かなショパン。本選の「幻想ポロネーズ」では、進藤実優のただならぬ思いを感じさせる演奏を聴きながら、この作品は「ショパンの走馬灯なのだな」と改めて認識し、「晩年のショパンはどのような思いで書いたんだろう」と思いをはせた。
▽街並みに旋律を思い浮かべ
ワルシャワでの取材は、まさに日常のあらゆる場面でショパンの音楽を意識した日々だった。成田空港をたつ直前のLOTポーランド航空の機内にはショパンの名曲が流れ、中でも憂いを帯びた「ワルツ第7番 嬰ハ短調」を聴きながらシートベルトを締めた時は「ショパンが戻ることのなかったワルシャワに今から向かう」という気持ちが高まり、不思議な感動を覚えた。
ワルシャワはまさにショパンの音楽の源泉を感じさせる素朴で美しい街だ。もちろんショパンが実際に見た光景とは異なるものの、曇りの日の早朝の風景は、淡い街路樹の紅葉と退廃的な建物が調和して「マズルカ」のような哀愁を思わせたし、中心部の円形の交差点に車や路面電車が行き交うのをホテルの部屋から見下ろしていると、なんとなくピアノ協奏曲第2番の第3楽章のころころ転がって行くような旋律が思い浮かんだ。ショパンの心臓が安置されている聖十字架教会で命日に開かれたミサには、寒さを感じなくなほど大勢の人が集まり、ポーランド人にとっていかにショパンが大切な存在なのかも実感した。
▽一言で表せない複雑な味わい
一緒に取材した特派員と食べた料理も思い出深い。酸っぱいながらコクがあり、一度食べるとやみつきになるポーランドのスープ「ジュレック」に、たっぷりと肉が詰まった「ピエロギ」。特派員から、ポーランド料理は「甘い」「辛い」といった一言では言い表せない複雑な味わいを持っていると聞き「まさにショパンの音楽そのものだ」と膝を打った。
「ショパンは甘すぎて苦手」という人もいるかもしれない。筆者もクラシック音楽を聴き始めた頃はそうだった。個人的なショパンとの「出会い」は、かつて警察担当の記者として連日取材先を「夜回り」していた頃だ。ふと思い立ち、取材先を待ちながらイヤホンで「マズルカ」を一曲目から順番に聴いたことがあった。冷たい風が吹き付ける冬の星空の下、一向に帰ってこない取材先を待ちながら聴く「マズルカ」ほどその時の孤独と焦燥に寄り添ってくれる音楽はなく、それからショパンに興味を持つようになった。
甘いメロディーが時に切なく、悲しいハーモニーが時に優しい。若々しさの中に達観があり、枯れた味わいの中に強さがある。その音楽はまさに私たちが日常で抱く感情そのもの。それでいてどんな時も決して優雅さを失わない姿勢には、人間の矜持(きょうじ)すら感じる。コンクールを通してショパンの音楽に改めて魅力を感じた人も多いはずだ。5年後の出場者はどんなショパンを聴かせてくれるのか。5年後の自分はショパンのどこに魅力を感じるのか。そんな楽しみを抱きながら、これからもさまざまなショパンを聴き続けていこう。
× ×
「クレッシェンド!」は、若手実力派ピアニストが次々と登場して活気づく日本のクラシック音楽界を中心に、ピアノの魅力を伝える共同通信の特集企画です。