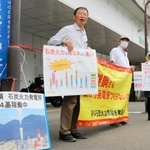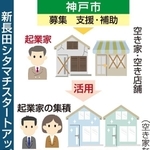■「神戸」と「兵庫」 明治期の地図で納得
半円の二つの弧を交差させたような形になっている神戸市章。市のシンボルとして山で光っていることは市民もよく知るが、ほかにも区役所の建物、市の広報誌、マンホールのふたなどいろんな場所や物にあしらわれているのを目にする。
この市章の由来を市に尋ねると、「扇形の二つの港をイメージしたようです。明治40年にできました」とのこと。二つの港? 現在の神戸には「神戸港」しかないはずだが…。
「130年ほど前まで兵庫と神戸という二つの港がありました。さらに言うと、兵庫の方が神戸よりはるかに発展していたのです」
そう話すのは、郷土史に詳しい鳥瞰図(ちょうかんず)絵師の青山大介さんだ。青山さんは、兵庫津(ひょうごのつ)(現在の兵庫区南部)と呼ばれ、近世まで大いに栄えた港町を研究し、約150年前の町並みを忠実に再現して描いた。
兵庫と神戸。確かに、明治時代に作られた地図を見ると、「兵庫港」「神戸港」とはっきりと記されている。また、おそらくは両地域を指しているのだろう、「兵神」という言葉もよく目にする。
「今では同じ神戸市ですが、両地域の間には湊川が流れていました。兵庫と神戸は互いに『よその地域』という意識があったと思いますよ」
湊川は1901(明治34)年、現在の場所に付け替えられた。湊川が流れていた場所が埋め立てられて「新開地」が誕生し、東の浅草と比べられるほどにぎわったのは有名な話だ。
1868年の開港のインパクトが強いためか、「神戸港」というと、どうしても元町・三宮方面をイメージしてしまう。
しかし「そうではなく、元々は兵庫しかなかった」と青山さん。「開港後、中心地は兵庫から神戸へと移りましたが、旧兵庫港は港町として1300年近くにわたる長い歴史を持っています」
青山さんが描いた鳥瞰図からは、農村地帯が多かった時代にあって、港付近にかなりの数の民家が密集していたことが分かる。
神戸の港の中心だった兵庫港、そして、その源流となった兵庫津。取材を進めると、たくさんの驚きが待っていた。
◇
記者がぶらっと歩いて、まちの魅力をリポートする「てくてく神戸」。第3弾は、昨秋、展示施設が開館し、注目されている神戸港のルーツ「兵庫津」を舞台にお届けします。
【アーカイブ】
■布引編はこちら
■旧居留地編はこちら

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
文化神戸

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸#インスタ

-
神戸地方行政

-
但馬神戸

-
スポーツ神戸#インスタ

-
教育神戸

-
神戸教育

-
神戸

-
文化神戸神戸ジャズ100年

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
地方行政神戸

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸山口組分裂騒動

-
神戸

-
文化神戸阪神

-
神戸

-
神戸

-
神戸中学スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
スポーツヴィッセル神戸

-
神戸

-
西播神戸

-
神戸

-
神戸防災

-
神戸ウクライナ侵攻#インスタ

-
神戸

-
神戸中学スポーツ中学総体

-
神戸文化

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸ヴィッセル#インスタ

-
神戸医療

-
三田選挙地方行政神戸

-
神戸地方行政

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸三宮再整備スクープラボ

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸未来を変える

-
防災神戸

-
防災神戸

-
神戸

-
神戸地方行政

-
神戸地方行政

-
神戸

-
文化阪神明石神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
スポーツ神戸

-
神戸神戸空港

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸#インスタ

-
神戸淡路

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸

-
教育神戸

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸地方行政

-
神戸

-
姫路神戸

-
神戸

-
神戸

-
MARUDORI神戸