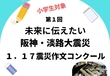東京電力福島第1原発の処理水海洋放出を受けて中国が実施している日本産水産物の全面禁輸措置が、ようやく解除される見通しになった。日中両政府が手続きを始めることで合意した。
懸案解決に向け一歩前進した形だが、まだ不十分だ。福島県や茨城県など10都県は解除の対象に入らず、禁輸は続く。中国が処理水を「核汚染水」と非難し、科学的根拠を示さずに一方的に輸入を停止したのは、巨大市場を武器にした威圧行為にほかならない。
習近平指導部は一刻も早く不当な措置をやめるべきだ。日本政府は引き続き規制の全面撤廃を強く働きかけねばならない。
現時点で日本からの輸出再開時期は決まっていない。中国側が日本の輸出業者を再登録する必要があり、少なくとも数カ月はかかるという。水産物を製造加工する施設の放射性物質の検査や、産地の証明書が必要になる。中国は手続きの迅速化に最大限努めてもらいたい。
処理水の海洋放出は、国と東電が地元漁業者の反対を押し切って2023年8月に始めた。国内外に前例がなく、国際原子力機関(IAEA)と連携して処理水のモニタリング(監視)体制を敷いてきた。これまでの検査で「国際的な基準に合致する」と確認されている。
中国が態度を軟化させた背景には、トランプ米政権への警戒感から対日関係の改善を急ぎたいとの思惑がうかがえる。禁輸で国内の水産物加工業者が影響を受け、経済界からの圧力も高まっていた。昨年9月、IAEAのモニタリング下で中国が海水などを試料採取することを日本が認め、両国間で禁輸解除へ向けた協議を続けてきた。
気になる点がある。このたびの合意について中国の税関当局は「技術的進展があった」と発表し、「輸入」の表現は使わなかった。台湾問題などで日本をけん制するために禁輸解除を「外交カード」として使う可能性もあるのではないか。警戒を怠るべきではないだろう。
禁輸措置によりホタテやブリの産地は大きな打撃を受けた。代表例が北海道だ。輸出先を米国やベトナムに振り替えてきた。兵庫県では干しナマコやカキの販路を東南アジアに広げ、影響を抑えた。ただ今度は米国が高関税を課すなど先行きは不透明だ。日本国内での消費喚起や輸出先の多角化が一層重要になる。
在留邦人の拘束や尖閣諸島周辺での領空侵犯・領海侵入など日中間の課題は山積する。関係改善を真に目指すのであれば、これらの解決へ向けて中国が着実に行動に移すことが何より求められる。