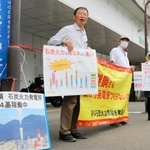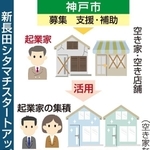1868年、神戸は開港し、多くの外国人が居留地や雑居地に住み始めた。
布引の滝は、異人館が並ぶ北野周辺からほど近い。和風の観光スポットとして注目を集め、84(明治17)年に英国の出版社が発刊した日本旅行案内の本にも、代表的な観光地として取り上げられたという。
滝を訪れる客を相手に商売をしたのが一帯に点在していた茶屋だ。布引の歴史に詳しい神戸大学特命講師の小代薫さんによると、滝の周辺だけでも、数十軒の茶屋や土産物屋が並んでいたとのこと。ただ、今も当時の面影を残すのは「おんたき茶屋」だけになった。
この茶屋の4代目当主、山口公子さんによると、現在の名前で営業を始めたのは1914(大正3)年のこと。茶屋自体はさらに古く、明治時代の創業だという。優に100年を超えて営業を続ける老舗だ。
山口さんは「自然と隣り合わせの店。土砂災害や震災を乗り越え、こんな山の中でよく続けられたものだと感心します」と話す。
1級建築士でもある小代さんは茶屋内部の造りを調べ、明治時代以降、増築や修理はあったものの大きな改変はなく現在に至っていることを確かめた。
布引遊園地をルーツに、かつての店名は「去来軒」だったともされる。小代さんは専門家として「明治期の行楽と建築の形式を伝える現存唯一の貴重な建物」と評価する。
昔の絵図や写真を見ても、雄滝(おんたき)が間近に見えるこの絶景スポットに建物があったのはほぼ間違いないようだ。平安貴族も頻繁に訪れたという布引の滝。現在の建物は明治以前からあったのか、それともどこかのタイミングで建て変わったのか-。
歴史を重ねた場所を訪れると、ついつい想像が膨らむ。(安福直剛)
【バックナンバー】
【アーカイブ】■旧居留地編はこちら

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
文化神戸

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸#インスタ

-
神戸地方行政

-
但馬神戸

-
スポーツ神戸#インスタ

-
教育神戸

-
神戸教育

-
神戸

-
文化神戸神戸ジャズ100年

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
地方行政神戸

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸山口組分裂騒動

-
神戸

-
文化神戸阪神

-
神戸

-
神戸

-
神戸中学スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
スポーツヴィッセル神戸

-
神戸

-
西播神戸

-
神戸

-
神戸防災

-
神戸ウクライナ侵攻#インスタ

-
神戸

-
神戸中学スポーツ中学総体

-
神戸文化

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸ヴィッセル#インスタ

-
神戸医療

-
三田選挙地方行政神戸

-
神戸地方行政

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸三宮再整備スクープラボ

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸未来を変える

-
防災神戸

-
防災神戸

-
神戸

-
神戸地方行政

-
神戸地方行政

-
神戸

-
文化阪神明石神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
スポーツ神戸

-
神戸神戸空港

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸#インスタ

-
神戸淡路

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸

-
教育神戸

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸地方行政

-
神戸

-
姫路神戸

-
神戸

-
神戸

-
MARUDORI神戸