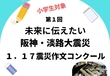日米間の懸案だった関税交渉が決着した。日本車への関税を当初示した27・5%から15%に引き下げ、「相互関税」にも特例を設ける。トランプ大統領は大統領令に署名した。
7月に一度は合意したが、日本の主張がどこまで受け入れられたか曖昧な点が多く、交渉が続いていた。自動車の関税引き下げが明示され経済界は歓迎するものの、以前の2・5%に比べ大幅引き上げに変わりはない。悪影響は避けられまい。
両国が交わした覚書は日本に巨額の対米投資を求め、米国が実行状況に不満を持てば関税引き上げもあり得る内容だ。トランプ氏の考え次第で状況が一変しかねず、交渉決着といえども安心感は持てない。
覚書によると、トランプ氏の任期が終わる2029年1月までに日本は5500億ドル(約80兆円)の対米投資を実施する。米国側で構成する委員会が示す投資先候補の中からトランプ氏が選ぶ。委員会に上げる案件は日米で協議する。
主導権は米国が握る形だ。日本が途中で投資をやめれば関税引き上げにつながりかねず、採算が合わなくなっても撤退できない。投資利益は一定水準まで日米で折半し、それ以上は米国が9割を得る。
極めて不平等な内容である。さらにトランプ氏は「利益の9割を米国が受け取る」と主張している。覚書の内容と矛盾しないか、日本政府は米国側と確認する必要がある。
一連の交渉では、巨額投資を日本に約束させるため共同声明や覚書の作成を米国が求めた。文書化の段階でさらに譲歩を迫られると考えて日本は拒んだが、後に米国が自国に有利な解釈を押し通すのを防ぐため、本来なら7月の合意段階で文書を交わすのが筋ではなかったか。
今月5日、米移民捜査当局は不法滞在や不法就労の疑いでジョージア州にある韓国企業の工場を捜索し、外国人労働者475人を拘束した。うち300人は韓国人で、日本人も含まれていた。トランプ政権が掲げる強硬な不法移民対策の一環だが、実際に不法行為があったかは別にして、自国の従業員が大量に拘束されるリスクを考えれば、海外企業が米国への投資に二の足を踏む事態が想定される。
米国は日韓など主要国に、関税引き下げに応じる代わりに巨額の投資を求める交渉を繰り返した。一方で、企業の投資意欲をそぐ政策にも力を入れるのは理解に苦しむ。
関税引き上げで製造業を復権させ雇用を増やす-。トランプ氏はそう訴えるが、労働コストの高さが製造業の競争力を失わせ、移民に頼る経済構造を招いた現実も、直視しなければならない。