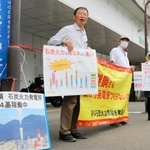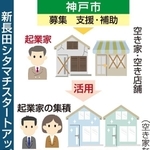■北から西へ囲うように配置
かつて兵庫津(ひょうごのつ)と呼ばれていた神戸市兵庫区南部を歩いていると、兵庫大仏で有名な能福寺をはじめ、寺院が非常に多いことに気づいた。
その理由について、兵庫県地域振興課の山下史朗さんは2点を挙げた。
「一つはやはり人口が密集しており檀家(だんか)が多かったためです。もう一つは、この地が城下町として整備された点が大きいでしょう」
一つ目の理由は分かったが、二つ目についてはうまくのみ込めなかった。これまでの取材では、兵庫津というのは確か港町だったはず。城下町? いつからだろう。
山下さんによると、日宋、日明貿易の拠点として発展した兵庫津は、国内有数の港町として栄えた。しかし、戦国時代に入ると、戦時中の食糧補給や多くの武士が一度に多く出入りする際の拠点として注目されるようになったのだという。
「城そのものだけではなく、城下町全体を守ることが城主の役割でした。そこで寺が大きな役割を果たしたのです」
寺は広い本堂や境内があるため、敵が容易に町の中に攻め入るのを防ぎ、味方の軍勢が大挙して待ち伏せする場としてもうってつけだったという。
「この図面を見てください。兵庫津のまちの北側には寺がずらりと並んでいます。城主が寺を配したと考えるのが自然です」
江戸時代の町並みを再現した図面を見ると、兵庫津の東は海で、北から西にかけて多くの寺が並んでいた。
そして、南西から南にかけて天然の大きな堀があったという。周囲には堤防も築かれ、これらが町を守る役割を果たしたようだ。
古くから港町として発展してきた兵庫津が軍事色の強い城下町として整備されたという説明は紛れもなく驚きだった。とはいえ、いかんせん、その面影が今ではほぼ残っていない。
眼前では、ショッピングモールに多くの買い物客が出入りし、兵庫運河がゆったりと水をたたえている。
「城下町」と呼ぶからには、当然、城があったはずだ。その点を山下さんに聞いてみた。
「もちろんありました。その名の通り兵庫城です。信長や秀吉とも深い関わりがあったんですよ」
日本史を彩るビッグネームが飛び出した。
=随時掲載=
【バックナンバー】
(4)室町幕府の日明貿易拠点 義満は兵庫が大好き
(3)平安の「山、海へ行く」、5万人動員し人工島築く
(2)港都神戸の原点 著名人の先祖ずらり
(1)神戸市章 二つの弧は二つの港?
【アーカイブ】
■布引編はこちら
■旧居留地編はこちら

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
文化神戸

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸#インスタ

-
神戸地方行政

-
但馬神戸

-
スポーツ神戸#インスタ

-
教育神戸

-
神戸教育

-
神戸

-
文化神戸神戸ジャズ100年

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
地方行政神戸

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸山口組分裂騒動

-
神戸

-
文化神戸阪神

-
神戸

-
神戸

-
神戸中学スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
スポーツヴィッセル神戸

-
神戸

-
西播神戸

-
神戸

-
神戸防災

-
神戸ウクライナ侵攻#インスタ

-
神戸

-
神戸中学スポーツ中学総体

-
神戸文化

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸ヴィッセル#インスタ

-
神戸医療

-
三田選挙地方行政神戸

-
神戸地方行政

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸三宮再整備スクープラボ

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸未来を変える

-
防災神戸

-
防災神戸

-
神戸

-
神戸地方行政

-
神戸地方行政

-
神戸

-
文化阪神明石神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
スポーツ神戸

-
神戸神戸空港

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸#インスタ

-
神戸淡路

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸

-
教育神戸

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸地方行政

-
神戸

-
姫路神戸

-
神戸

-
神戸

-
MARUDORI神戸