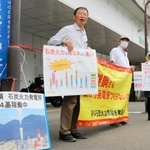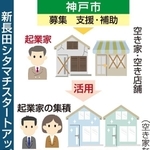■江戸時代に最盛期 宿屋や料理屋が密集
JR兵庫駅の少し東側、柳原蛭子(ひるこ)神社と福海(ふくかい)寺(いずれも神戸市兵庫区西柳原町)の間に少し変わった道路がある。幹線道路を斜めに突き刺すかのように通る細い一方通行。まさにこの道こそが、西国街道だ。
江戸時代、京都と西方を結ぶ道として多くの人々が行き交った。神戸市内の西国街道は、一部が国道2号や28号に当たり、今も幹線道路として利用されている。
そんな街道は、迅速に往来できるよう、基本的に直線が多い。一方で、兵庫津(ひょうごのつ)付近(現在の兵庫区南部)では少し事情が異なる。
地図を見ると、この辺りで明らかに道路が回り道をしている。斜めに突き刺しているように見えたあの道とも関係がありそうだ。
幕末の兵庫津の鳥瞰図(ちょうかんず)を制作した絵師の青山大介さんは「古くは山陽道と呼ばれた道を江戸幕府が再整備したのが西国街道です」と説明。
「元々は直線でしたが、兵庫津に人々が立ち寄るようになったため、こんな曲がり方をするようになったのでは」と教えてくれた。
つまり兵庫津は、幹線道路をそれてでも寄り道する価値があったまちだった。青山さんは「この地の繁栄を物語っています」と指摘する。
大輪田泊(おおわだのとまり)と呼ばれる小さな港だった兵庫津は江戸時代に最盛期を迎え、宿屋や料理屋が密集していた。「まだ車もなかった時代に、このまちを通らずに次へ向かおうという人はよほどの健脚ですよ」と青山さんは笑った。なるほど、今の高速道路のサービスエリアみたいな所だったのかと一人で合点した。
江戸時代の商人よろしく、柳原蛭子神社のそばを通り、例の斜めの道を東へ向かってみた。直角になっている場所(兵庫区本町周辺)はかつて「札場の辻」と呼ばれ、まちの中心部だったそうだが、今は案内板と小さな標柱があるだけだ。
標柱を見ると「左 築(島寺)」と書かれていた。ん? 左といえば、たった今、歩いてきた西の方角だ。
標柱は本来、向かい側にあったのだろう。一人寂しく「逆ちゃうん?」と石に突っ込みを入れて西国街道を北へ向かう。すると、また新たな発見があった。
【バックナンバー】
(番外編)市章は「カウベ」の「カ」?
(6)幻の兵庫城 天下人の夢の跡、発見
(5)軍事色強い城下町 寺院は町の防御役
(4)室町幕府の日明貿易拠点 義満は兵庫が大好き
(3)平安の「山、海へ行く」、5万人動員し人工島築く
(2)港都神戸の原点 著名人の先祖ずらり
(1)神戸市章 二つの弧は二つの港?
【アーカイブ】
■布引編はこちら
■旧居留地編はこちら

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
文化神戸

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸#インスタ

-
神戸地方行政

-
但馬神戸

-
スポーツ神戸#インスタ

-
教育神戸

-
神戸教育

-
神戸

-
文化神戸神戸ジャズ100年

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
地方行政神戸

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸山口組分裂騒動

-
神戸

-
文化神戸阪神

-
神戸

-
神戸

-
神戸中学スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
スポーツヴィッセル神戸

-
神戸

-
西播神戸

-
神戸

-
神戸防災

-
神戸ウクライナ侵攻#インスタ

-
神戸

-
神戸中学スポーツ中学総体

-
神戸文化

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸ヴィッセル#インスタ

-
神戸医療

-
三田選挙地方行政神戸

-
神戸地方行政

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸三宮再整備スクープラボ

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸未来を変える

-
防災神戸

-
防災神戸

-
神戸

-
神戸地方行政

-
神戸地方行政

-
神戸

-
文化阪神明石神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
スポーツ神戸

-
神戸神戸空港

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸#インスタ

-
神戸淡路

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸

-
教育神戸

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸地方行政

-
神戸

-
姫路神戸

-
神戸

-
神戸

-
MARUDORI神戸