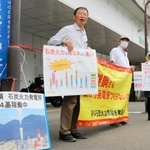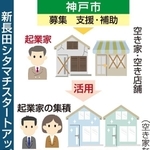■敵を警戒「遠見遮断」の工夫
前回紹介した柳原蛭子(ひるこ)神社と福海(ふくかい)寺(いずれも神戸市兵庫区西柳原町)の間を斜めに走る道路。この出入り口近くに石碑と案内板が立っており、「西国街道 兵庫 西惣門跡」とある。
この道(西国街道)を進み、兵庫津(ひょうごのつ)の中心地だったという場所を直角に曲がる。北に歩いていくと、湊八幡神社(同市兵庫区兵庫町1)の近くで同じような石碑を見つけた。今度は「西国街道 兵庫 湊口惣門跡」とある。
この二つには何か関係がありそうだ。郷土史に詳しい鳥瞰図(ちょうかんず)絵師の青山大介さんに尋ねると、「どちらも兵庫津のまちの出入り口にあった門の跡」という。
兵庫津が一時期、城下町として整備されたことはこれまで紹介した通りだが、その際、まちを囲む堤防(土塁)とともに築かれたのが二つの門のようだ。
「要するに、まちを守る城門です。見張りが付き、夜は閉まっていた時期もあったようですよ」
戦国時代、織田信長の家臣が築いた兵庫城、そして、兵庫の城下町。この頃は西方の毛利氏との対立もあり、西側の惣門付近は特に警戒が厳しかったようだ。
青山さんによると、西側は門を開いても外からまちを見渡せないよう、道路を曲がらせる「遠見遮断(とおみしゃだん)」という工夫がなされていた。
遠見遮断の西国街道と、玄関口にあった二つの門。戦国期の兵庫津を語る上で興味深い仕組みだが、残念ながら面影はない。
唯一の手掛かりは、神戸市などが実施した柳原惣門(西惣門)の復元計画だ。同市教育委員会は2002年、歴史遺産を生かしたまちづくりを後押ししようと、惣門跡を発掘。その調査データや他の場所で残る惣門を参考に、推定復元図を制作した。兵庫区役所に残るその図面データを入手できた。
資料によると、高さは5メートルほどで、立派な門だったようだ。実際に復元すれば面白いと思うのだが、市文化財課も兵庫区役所も「ちょっとそこまでは…」という回答だった。
兵庫津は明治時代、運河開削などさまざまな近代化が進められた。城跡をはじめ、城下町を囲っていた堤防や惣門も壊されたという。新たな時代の創造には必要な破壊だったのだろうが、歴史文化が薫るまちだけに、今となっては少し惜しい気もする。
【バックナンバー】
(7)西国街道 まちの繁栄物語る回り道
(番外編)市章は「カウベ」の「カ」?
(6)幻の兵庫城 天下人の夢の跡、発見
(5)軍事色強い城下町 寺院は町の防御役
(4)室町幕府の日明貿易拠点 義満は兵庫が大好き
(3)平安の「山、海へ行く」、5万人動員し人工島築く
(2)港都神戸の原点 著名人の先祖ずらり
(1)神戸市章 二つの弧は二つの港?
【アーカイブ】
■布引編はこちら
■旧居留地編はこちら

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
文化神戸

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸#インスタ

-
神戸地方行政

-
但馬神戸

-
スポーツ神戸#インスタ

-
教育神戸

-
神戸教育

-
神戸

-
文化神戸神戸ジャズ100年

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
地方行政神戸

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸山口組分裂騒動

-
神戸

-
文化神戸阪神

-
神戸

-
神戸

-
神戸中学スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
スポーツヴィッセル神戸

-
神戸

-
西播神戸

-
神戸

-
神戸防災

-
神戸ウクライナ侵攻#インスタ

-
神戸

-
神戸中学スポーツ中学総体

-
神戸文化

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸ヴィッセル#インスタ

-
神戸医療

-
三田選挙地方行政神戸

-
神戸地方行政

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸三宮再整備スクープラボ

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸未来を変える

-
防災神戸

-
防災神戸

-
神戸

-
神戸地方行政

-
神戸地方行政

-
神戸

-
文化阪神明石神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
スポーツ神戸

-
神戸神戸空港

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸#インスタ

-
神戸淡路

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸

-
教育神戸

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸地方行政

-
神戸

-
姫路神戸

-
神戸

-
神戸

-
MARUDORI神戸