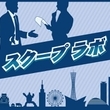障害者や高齢者ら災害弱者への支援のあり方も問われた阪神・淡路大震災。災害弱者のうち聴覚障害者をめぐる状況は、19年たち、どう変わったのか。当事者で兵庫県立聴覚障害者情報センター(神戸市灘区)の嘉田眞典所長(48)に、当時の体験や今後の課題などを聞いた。(貝原加奈)
-発生当時、県聴覚障害者協会の職員だった。
「三田市に住み、自宅は無事だった。早朝、車で神戸市中央区の協会事務所へ向かった。パジャマ姿の住民や崩れ落ちた建物などを見て、衝撃を受けた。ファクスは停電で使えず、幹部らに連絡をとることはできなかった。翌日の18日、自宅に全日本ろうあ連盟からファクスが届いた。『無事ですか。神戸の様子を把握してほしい』という内容だった」
-同連盟の指示で、神戸ろうあ協会などと県聴覚障害者救援対策本部を21日に設けた。
「神戸、阪神地区の避難所を自転車で回り、当事者の安否を確認し、生活に必要な情報を載せたニュースを配った。全国のろうあ協会や手話サークルの人たちが毎日、活動してくれた。神戸市に住んでいた約5千人の聴覚障害者のうち、1500人ほどの安否を確認できた」
-避難所での様子は。
「救援物資の配布を告げる案内放送が聞こえず、列を見てから最後尾に並ぶと、もらえない場合もあった。テレビの手話ニュースは他の報道番組に変わり、生放送の番組は字幕がなかった。情報が入らず、周囲の人とコミュニケーションも取れず、孤立しがちだった。日常生活での困難が、より浮き彫りになったといえる」
-その後、さまざまな取り組みが進んだ。
「神戸市に働き掛け、行政の窓口に手話通訳者を日常的に配置してもらった」
「耳が不自由な高齢者や、聴覚と視覚の障害がある重複障害者らの存在が広く認識された。生きがいづくりのための作業所や、手話が通じる高齢者施設の開設につながった。災害弱者を守る取り組みが広がったともいえる」
-16年後に東日本大震災。教訓は生かされたのか。
「聴覚障害者の死亡割合は、住民全体の約2倍だった。大津波警報に気付かずに逃げ遅れた当事者が、多いのだろう。避難所での情報伝達も音声が中心で、阪神・淡路とあまり変わっていなかった。東日本は、阪神・淡路に比べ、被災が広範囲だったため、支援も行き届きにくかった」
-今後の課題は。
「災害時の情報を保障することは、大きな課題。防災無線が聞こえない人にどう情報を届けるか、みんなが考えていかなければ」
「テレビの緊急放送には字幕や手話が付いていない。全日本ろうあ連盟から国などに要望を出しているが、なかなか実現しない。避難所で情報提供する際、紙やホワイトボードを利用する方法も広げていく必要がある」
-情報センターとしてどう取り組むか。また市民へのメッセージを。
「学習会で震災時の体験を発信するなど、障害者自身の災害意識を高められるようにする。また、特性を理解してもらえるよう、市民を対象にしたセミナーや、交流の場を積極的に企画する」
「県内で障害者手帳を持つ聴覚障害者は約1万8千人。災害の形は予想できない。そのとき重要となるのは、身近な人の力だ。健常者も障害者も地域で日常的につながり、顔見知りになることを心掛けてほしい」
【かだ・まさのり】1965年1月、大阪市生まれ。3歳の時、注射の副作用で聴力を失う。尼崎市立尼崎高校卒。91年4月から兵庫県聴覚障害者協会に勤務、2005年5月より現職。
【体験を教訓に 冊子を製作】
兵庫県聴覚障害者協会は、阪神・淡路大震災後、当事者の被害や救援の状況をまとめた冊子を作り、現在も販売。ほかに、当時の体験を紹介したDVD、支援のあり方をまとめたハンドブックもある。県聴覚障害者情報センターTEL078・805・4175