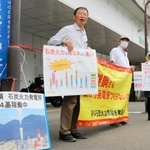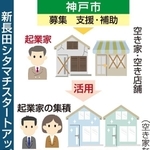明治初頭、神戸港の有力者たちで組織する民間企業「花園社」が整備した布引遊園地。神戸大学特命講師の小代薫さんによると、彼らの動きは神戸特有で、結果として日本の公園制度の整備につながったという。
19世紀後半に発足した明治新政府は、体制転換の直後で財政難に苦しんだ。当時の大蔵省は全国にある官有林を民間に払い下げる(売却する)ことで当面の財源を確保しようとしたが、そこで布引遊園地の中にある官有林が問題になったという。
その理由を小代さんは説明する。
「大蔵省から払い下げの命令がきた際、遊園地は整備をほぼ終えていました。せっかく整備してにぎわい始めたところなのに、樹木を伐採してしまうと台無しになりますよね」
両者の間に入ったのが、当時の兵庫県知事だった神田孝平(たかひら)という人物だ。大蔵省の言いなりにならず、逆に布引遊園地の重要性を国に説いたという。
一体、どう説得したのだろうか。「簡単に言うと、官有林を伐採して売るよりも、行楽地として繁盛させて課税した方がいいですよって伝えたのです」
明治5年のことだ。そして、なんとこの案が通った。そればかりか、妙案を得たとばかりに太政官(だじょうかん)(国の最高行政機関)は翌年、公園設置の布告を全国に発令。これにより、日本の景勝地や寺社境内地、城跡周辺の緑地が伐採されずに保護されることになったのだという。
小代さんは強調する。「布引遊園地に関わる神田の発想と行動は、日本の美しい自然景観や行楽の場を残すことにつながったと言えます」。背景には、経済学者でもあった神田が、居留地の外国人が公園整備を行う様子を知事として見届けていた経験が大きかったと指摘した。
「明治初頭という同時期に、神戸の近い場所に二つの遊園地(布引遊園地と東遊園地)ができたことは偶然ではありません」
今も形として残っているのは東遊園地だけだ。ただ布引遊園地の残した恩恵、緑豊かな自然風土は、現代に生きる私たちも確かに享受している。(安福直剛)
【バックナンバー】
(9)貿易商らでつくる民間企業「花園社」 行楽地として整備
(8)布引礦泉所の創業 川崎造船から派生
(7)創業123年「布引礦泉所」 名水販売の歴史重ね
(6)貯水池 希少な「かくれ滝」
(5)水の量少なくない? 壮大な滝は雨次第
(4)擬木の手すり 大正期製造か、登山道ずらり
(3)老舗茶屋 明治期の建築今に
(2)去来軒 消えた屋号の謎
(1)「遊園地」 土産物屋、茶屋にぎわう
【アーカイブ】
■旧居留地編はこちら

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
文化神戸

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸#インスタ

-
神戸地方行政

-
但馬神戸

-
スポーツ神戸#インスタ

-
教育神戸

-
神戸教育

-
神戸

-
文化神戸神戸ジャズ100年

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
地方行政神戸

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸山口組分裂騒動

-
神戸

-
文化神戸阪神

-
神戸

-
神戸

-
神戸中学スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
スポーツヴィッセル神戸

-
神戸

-
西播神戸

-
神戸

-
神戸防災

-
神戸ウクライナ侵攻#インスタ

-
神戸

-
神戸中学スポーツ中学総体

-
神戸文化

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸ヴィッセル#インスタ

-
神戸医療

-
三田選挙地方行政神戸

-
神戸地方行政

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸三宮再整備スクープラボ

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸未来を変える

-
防災神戸

-
防災神戸

-
神戸

-
神戸地方行政

-
神戸地方行政

-
神戸

-
文化阪神明石神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
スポーツ神戸

-
神戸神戸空港

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸#インスタ

-
神戸淡路

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸

-
教育神戸

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸地方行政

-
神戸

-
姫路神戸

-
神戸

-
神戸

-
MARUDORI神戸