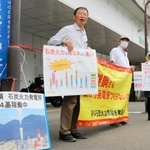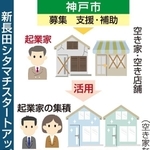■外交の大問題 明治政府が団結
兵庫大仏で有名な能福寺(神戸市兵庫区北逆瀬川町)には、他にも貴重な史跡「瀧(たき)善三郎正信碑」と刻まれた顕彰碑がある。そばには「神戸事件の犠牲者」との案内板が立つ。
瀧は備前(岡山)藩士で、神戸事件は1868年に三宮神社(同市中央区三宮町2)近くで起きた。藩士たちが西国街道を東進中、隊列を横切ろうとしたフランス人らと衝突し銃撃戦に。外交問題へと発展し、瀧は全ての責任をとって外国要人らの眼前で切腹した。
一見、事件とは何の関わりもなさそうな兵庫津(ひょうごのつ)の地に碑があるのは、瀧が自裁を遂げたのが兵庫区南仲町の永福寺だったからだ。
「大きな寺でしたし、切腹という重要な儀式を行うに当たって格式ある場が選ばれたのでしょう」
そう話すのは、県立兵庫津ミュージアムの多賀茂治学芸員だ。ただ、この寺は戦争で焼失してしまい、碑は1969年に近くの能福寺に移されて今に至る。
ちなみに、瀧たちは事件の直前、兵庫津の浜本陣(大名の宿泊休憩施設)で昼食をとってから東へ向かった。この事件は何かと兵庫津と縁が深い。
長い鎖国時代が終わった後、国内では日本人と外国人との衝突が各地で起きた。その中でも神戸事件は特別な意味を持つという。
「江戸から明治へと移る激動の時代にあって、神戸事件の影響は日本全体に及ぶものでした」と多賀さん。「事件直後、日本の外交の中心地はここ兵庫になったんです」と指摘する。
発生場所は開港間もない神戸港近くだった。事件を受け、居留地周辺は武装した欧米人が占拠し、港にいた日本の船は捕らえられた。さらに、日本人が利用する宿や店には外国側からこんな貼り紙が配られたという。
「備前藩だけの問題ではない。全国で災難が起きることも覚悟するように」
これは穏やかではない。明らかな威嚇である。こんなに怒らないでもいいではないか。
「外国からすれば、日本は開国したのに『やはりこの国は敵なのか』という警戒心が生まれたのでしょう。日本政府も戦争を覚悟したかもしれません」
日本人にとって武士の隊列を横切ることは無礼であり、備前藩士の対応はごく自然だったと思われる。しかし、最終的には「備前藩の責任を明確にすべし」となり、瀧が全責任を負うことになった。
「事件を機に、各藩の寄せ集めだった新政府が『対外国』という点で団結しました。また、外国側の視点で見ると、正式な外交相手が幕府ではなく新政府となったわけで、一つの時代の分岐点と言えそうです」
能福寺には今も各地から参拝者が訪れ、供養が続けられている。「日本を守ったラストサムライ」とも呼ばれる瀧善三郎。一人の男の残した足跡は、兵庫・神戸の地でも確かに刻まれている。
【バックナンバー】
(9)初代県庁 明治政府、城跡利用し統治
(8)二つの惣門跡 城下町守る強固な城門
(7)西国街道 まちの繁栄物語る回り道
(番外編)市章は「カウベ」の「カ」?
(6)幻の兵庫城 天下人の夢の跡、発見
(5)軍事色強い城下町 寺院は町の防御役
(4)室町幕府の日明貿易拠点 義満は兵庫が大好き
(3)平安の「山、海へ行く」、5万人動員し人工島築く
(2)港都神戸の原点 著名人の先祖ずらり
(1)神戸市章 二つの弧は二つの港?
【アーカイブ】
■布引編はこちら
■旧居留地編はこちら

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
文化神戸

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸#インスタ

-
神戸地方行政

-
但馬神戸

-
スポーツ神戸#インスタ

-
教育神戸

-
神戸教育

-
神戸

-
文化神戸神戸ジャズ100年

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
地方行政神戸

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸山口組分裂騒動

-
神戸

-
文化神戸阪神

-
神戸

-
神戸

-
神戸中学スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
スポーツヴィッセル神戸

-
神戸

-
西播神戸

-
神戸

-
神戸防災

-
神戸ウクライナ侵攻#インスタ

-
神戸

-
神戸中学スポーツ中学総体

-
神戸文化

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸ヴィッセル#インスタ

-
神戸医療

-
三田選挙地方行政神戸

-
神戸地方行政

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸三宮再整備スクープラボ

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸未来を変える

-
防災神戸

-
防災神戸

-
神戸

-
神戸地方行政

-
神戸地方行政

-
神戸

-
文化阪神明石神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
スポーツ神戸

-
神戸神戸空港

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸#インスタ

-
神戸淡路

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸

-
教育神戸

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸地方行政

-
神戸

-
姫路神戸

-
神戸

-
神戸

-
MARUDORI神戸