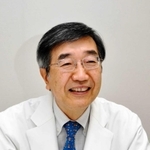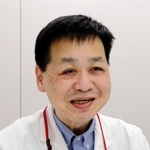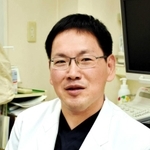高齢者の死因で注目されているのが、ものをのみ込む「嚥下(えんげ)」の機能が衰えて起きる誤嚥性肺炎です。誤嚥性肺炎の予防が、健康長寿にとって重要だと思います。
肺炎は、抗生物質の登場や栄養状態の改善により戦後減少しましたが、1980年以降、人口の高齢化や薬が効きにくくなる「耐性菌」の出現で増加が続いています。肺炎で死亡する人の95%以上が65歳以上といわれています。高齢になると嚥下機能が低下したり、細菌に対する抵抗力が落ちたりすることが影響しているようです。脳血管疾患は、治療薬や救急体制が進んで死亡例は減ったのですが、その後遺症で誤嚥性肺炎が増えているともいわれています。
誤嚥性肺炎は、口の中や食物、胃液などに存在する細菌が、空気の通り道である気道へ誤って入ることで起きます。食事中のむせやせき、唾液をのみ込めない、などの症状もありますが、睡眠中に知らない間に誤嚥をしていることもあります。
予防にはまず、インフルエンザワクチン接種に加え、多くの肺炎の原因とされる肺炎球菌のワクチン接種をお勧めします。お孫さんから感染して肺炎になる場合もあるので、お子さんのワクチン接種も重要です。お口のケアも大切です。高齢者は、唾液の減少や入れ歯の影響で細菌が口腔(こうくう)内で繁殖しやすいためです。歯磨きをしっかり行いましょう。誤嚥性肺炎を心配してお口から食べ物を取らないのは、かえってマイナスです。嚥下機能がさらに低下したり、かむ刺激が減るために脳の機能が低下したり、唾液が減少したりする恐れがあります。
気道に細菌を入りにくくするには、寝たままでなく、できるだけ椅子に座って、姿勢をよくして食べてください。液体は、とろみを付けてのみ込みやすくしましょう。嚥下や摂食のリハビリも有効です。会話はのどを動かし、嚥下機能の維持にも役立ちます。(聞き手・金井恒幸、協力・兵庫県予防医学協会)
【とみおか・ひろみ】1960年生まれ。京都大医学部卒。2006年に神戸市立医療センター西市民病院に赴任、09年から呼吸器内科部長。静岡県出身。神戸市垂水区在住。
肺炎
国内の死因上位はがん、心疾患、脳血管疾患の順が続いていたが、2011年に肺炎が脳血管疾患を抜いて3位になった。死因となった肺炎のうち多くが誤嚥性肺炎であるとされる。