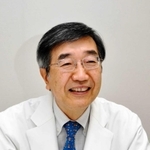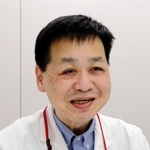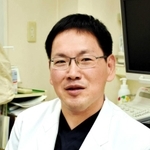音楽には不思議な力があります。17年前に特別養護老人ホームを訪ね歌の伴奏をしたとき、入所者の表情が見る見る変わるのに感動したのが、音楽療法を志すきっかけになりました。
その年に養成講座が始まった兵庫県音楽療法士の資格を取り、専門知識を生かしながら、心身の健康づくりをお手伝いしています。
最近は介護予防教室で指導する機会が増えました。認知症は誰でもなる病気ですが、少しでも進行を遅らせるため音楽療法を活用しています。
音楽は、遠い昔の記憶を引っ張り出してくれる効果があります。認知症が進行した高齢者でも、子どものころに親しんだ歌を口ずさむことができます。
さらに「この曲を歌っているのは誰でしょう」などと尋ねると、次々と記憶がよみがえることがあります。もし間違えても否定せず「そうですねえ」と受け入れます。自尊感情を高めるのは気持ちを落ち着かせる点で大切です。
歌を楽しみながら、脳機能を鍛える「脳トレ」も行っています。二つの課題を同時にする「デュアルタスク・トレーニング」がお勧めです。
例えば、懐かしい童謡や唱歌を歌いながら、リズムに合わせて手でグーチョキパーをつくったり、小さなお手玉を放り投げたりするだけでも効果的です。曲のフレーズごとに皆で振りを考えて、歌いながら体を動かして短期記憶を鍛える方法もあります。
楽器の演奏は、脳の活性化だけでなく、筋力トレーニングにもつながります。お勧めは卵マラカス。軽くて持ちやすく、すてきな音が出ます。楽器店で売っています。トーンチャイムという楽器もお勧め。振ると柔らかい音が響いて、何人かで演奏すると美しいハーモニーになります。
認知症の予防には、楽しいという気持ちや、「やったあ」という達成感がとても大切です。課題に取り組むときは、絶対に無理せず、成功体験につなげることがポイントです。音楽は、少し難しいことでも楽しく簡単に取り組めるようにしてくれます。
音楽療法は自宅で家族と一緒にできますが、ぜひ一度、療法士の指導を受けてほしいと思います。地域の福祉施設で行っているほか、一般の人向けには健康ライフプラザ(神戸市兵庫区駅南通5、TEL078・652・5202)などで教室を開いています。(聞き手・田中伸明、協力・兵庫県予防医学協会)
【おおぐし・ちえ】1960年生まれ。ヤマハ音楽講師(電子オルガン)を経て、2002年に第1期の兵庫県音楽療法士に。その後、日本音楽療法学会が認定する資格も取得。神戸市出身・在住。
大串さんが勧める三つの作法
一、歌と動きを組み合わせて認知症予防
一、負担が少ない楽器で脳と体を活性化
一、ぜひ一度、音楽療法に参加を
兵庫県音楽療法士
兵庫県が独自に認定する資格。被災者らの心のケアを目指し1999年度から養成講座を開設。2015年度までに352人が認定を受けた。施設向けに音楽療法士の派遣費用を県が補助する制度も。県音楽療法士会TEL078・261・9601