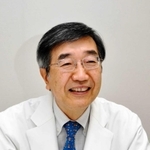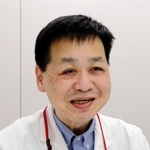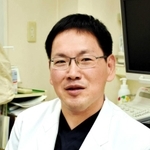かつて胃のもたれや痛みなどの症状は、胃がんや胃潰瘍を見分けるサインと考えられていました。ですが今は、そうした病気でなくても、胃の調子が悪い場合は対応が求められるようになりました。
転換を迎えた一つの理由は胃潰瘍や胃がんといった病気のメカニズムが分かってきたことです。原因となるのは胃の粘膜にすむピロリ菌です。免疫力の弱い小学低学年ごろまでに感染し、胃炎が続いて胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんを引き起こすのです。衛生状態と関連するので日本人は感染率が減っていますが、依然として注意が必要です。
ピロリ菌がいなければ胃がんにはほとんどなりません。ピロリ菌に加え、塩分の過剰摂取や喫煙、ストレス、体質が影響して発症しやすくなります。感染期間が長いとリスクが高まるので、早めの除菌をお勧めします。
では、検査で異常が見つからないのに胃の調子が悪い場合はどうすればいいのか。
胃や腸は人間の意思では動かせず、自律神経によって支配されています。ところが、自律神経はちょっとした感情や環境に影響を受けるのです。ストレスで心身がリラックスできないことが胃にも影響すると考えられます。そのため、自律神経の働きを正常化することが胃の症状を治す一つの鍵になります。
ストレスを抱えて、自律神経が悪影響を受けている人は多くいます。対策では座禅や瞑想(めいそう)も効果があると思いますが、決まった時間に食事をするなど規則正しい生活が大事です。睡眠、覚醒という日々のリズムをつくることが自律神経の安定に役立ちます。
20~30分程度、朝に散歩するのも有効です。太陽に当たると、セロトニンという物質の分泌にもつながります。これが減ると、うつ病になったり眠れなくなったりすることが知られています。
また、高齢の方は健康に対して大きな不安を持っておられます。胃の症状があっても画像検査で異常が見つからない場合、疲れなどのストレスが原因だと認識することはとても大事です。それだけで随分楽になるはずです。
検査で異常が見つからないのに胃の痛みやもたれ、早期満腹感などがいつも起こっているのが「機能性ディスペプシア」です。まだ慢性胃炎などと誤診されるケースが多く、医師にももっと知ってもらいたいと思っています。(聞き手・森 信弘、協力・兵庫県予防医学協会)
【みわ・ひろと】1956年堺市生まれ。82年、鹿児島大医学部卒。米ミシガン大医学部研究員などを経て、2004年から兵庫医科大主任教授、16年から副学長。専門は消化器内科一般と上部消化管疾患。
三輪さんが勧める三つの作法
一、食事や睡眠など規則正しい生活を送る
一、朝の20~30分の散歩など軽い運動をする
一、検査で異常がなければ自律神経の乱れを疑う
自律神経の働き
自分の意思と関係なく、消化器や心臓、ぼうこう、血管などをコントロールする。活動時に働く交感神経と、リラックスしたときに働く副交感神経があり、体の調子を整えている。脳幹と脊髄に中枢がある。