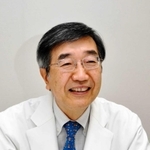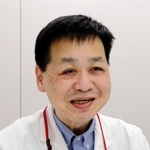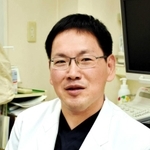最近は80代、90代の「超高齢者」も手術を受けられます。入院時は筋力を落とさないことも大切です。急性期の病院では、昔と違って手術当日から座ったり立ったりとリハビリを積極的に取り入れます。個別の事情はありますが、入院中も体を動かして筋力を維持することが、元の生活に少しでも早く戻るコツです。
高齢者は、環境の変化への適応力が低下しています。入院や治療の影響、体調の不具合で混乱してしまうこともよくあります。そんな時、湯飲みでも家族の写真でも見慣れた物があると落ち着けます。家族から「昼間はこうして過ごしている」などと、本人の生活パターンを教えてもらえると医師や看護師は助かります。予期せぬ合併症などを防ぐことにもつながります。
超高齢者になると、体の生理機能が低下します。そのため、一般の成人には「最適」な治療でも、高齢者では「食べる・歩く」などの生活機能が低下してしまうことがあります。医師から提案された治療が高齢者にとって一番良いのか、生活の質(QOL)が維持できるのか、本人も家族も迷われることが多いです。
「最後まで食事をおいしく食べたい」「トイレだけは自分でしたい」「どんなに弱っても1人暮らしがしたい」など、人によって大切にしたいことは違います。しかし、例えば、認知症が進むと言葉で表現することが難しくなることがあります。代理意思決定をする家族は、本人にとって何が一番良いことなのか分からず苦悩してしまいます。家族やかかりつけ医には、元気なうちから自分の希望や望む生活を話しておきましょう。
病気になった高齢者は、自分が家族や社会のお荷物になっていないだろうか、と心配されることがあります。言葉のかけ方次第では、存在意義の苦悩が高まってしまうこともあります。家族は「高齢者は何もできない」「理解できない」などと過小評価せず、ひとりの人として大切にされていると感じられるよう、本人の意思を尊重した関わり方をしてほしいと思います。
最後まで、その人らしく生きるのは大切なことです。ところが、日本では死について語ることがタブー視されがちなので、本人の望みが周囲に伝わりにくい現状があります。人生の最後について元気なうちから話しておくことが、その人らしい生き方を支えることにつながると思います。(聞き手・森 信弘、協力・兵庫県予防医学協会)
【はなふさ・ゆみこ】1967年、岡山県生まれ。89年に神戸市立医療センター中央市民病院に入職。2010年に神戸市看護大学大学院修了。日本看護協会から老人看護専門看護師の認定を受ける。神戸市長田区在住。
花房さんが勧める三つの作法
一、入院時は生活機能を落とさないようリハビリを
一、最後まで大切にしたいことを元気なうちに話す
一、家族は本人の意思を尊重した接し方を心掛ける
老人看護専門看護師
高齢者ケアの専門家として、複雑な健康問題に悩む高齢者の生活の質を向上させるため、高水準の看護を提供する。専門看護師は特定の専門分野で卓越した実践能力を持つ。現在は「がん」など11分野があり、日本看護協会が認定。