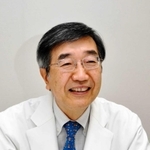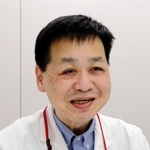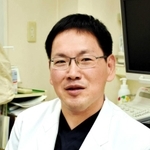「神戸輪っ鼓舞(わっこまい)」という和太鼓グループを22年前に立ち上げ、現在は練習を指導しています。メンバーは女性が中心で、70代半ばの方もいらっしゃいますが、皆さん本当にお元気です。
和太鼓の演奏は全身を動かしますし、練習中はずっとたたき続けています。みんなで一緒に楽しみながら、自然に体幹を鍛えることができます。演奏では時折、ばちを頭上高く差し上げます。和太鼓ならではの動きですが、この動作を繰り返すと「五十肩(ごじゅうかた)」で肩が痛む人も、次第に腕が上がるようになります。
輪っ鼓舞のメンバーは平均年齢が高く、50歳を過ぎてから始めた人もいます。リズムを体に染み込ませるのは大変ですが、常に課題を持ち、新しいことに挑戦する刺激が心身を若返らせてくれます。「ぼけてる暇がない」と笑い合っています。
太鼓をたたく体力を維持するため、ランニングなどで鍛える人もいます。それほど生活の一部として欠かせない存在になっています。とはいっても無理をする必要はありません。自分の力に応じてたたけばいいのです。輪っ鼓舞では、その人の個性に応じて振り付けを行い、本番で輝けるようにしています。ばちを振るうのがきつくなっても別の役割で演奏に参加できるよう、しの笛を習っている人もいます。
メンバーは親の介護に直面する人が多いです。私自身も母の世話をしましたが、その時も和太鼓の時間を持つことで、自分を支えられたかなと思います。同じ苦労をする者同士、何も言わなくても共感し合い、いざというときは助け合います。仲間を持つことは、心身の健康を保つために大切なことだと感じます。
別の和太鼓グループで教えている生徒さんで、82歳の女性がいます。楽譜を家のあちこちに張って練習に励み、少しずつですが着実に上達しています。「心と体がわくわくするねん」と喜んでいますが、とても素晴らしいことだと思います。
一方で、男性は途中でやめてしまう人が多いです。最初はなかなか思うように演奏できないものですが、プライドが邪魔して「できない自分」を許せないんですね。「少しずつできるようになっていく自分」を認めてあげてください。
そうすると、きっと世界が広がると思います。(聞き手・田中伸明、協力・兵庫県予防医学協会)
【ちが・まさこ】1954年大阪市生まれ。証券会社に7年勤めた後、保育士に転身。現在は障害のある子どもが通う「つくしっこ園」の園長を務める。和太鼓は保育園行事で指導するため始め、演奏歴24年。尼崎市在住。
値賀さんが勧める三つの作法
一、常に新しい課題を持ち、挑戦を続ける
一、介護などで大変な時も自分の時間を持つ
一、同じ志を持ち、助け合える仲間をつくる
神戸輪っ鼓舞
1994年結成。現在は24~74歳の15人が毎週火曜夜に練習し、演奏会も開く。22日午前10時~午後3時、神戸市中央区のフィッシュダンス音楽練習場で初心者向けのワークショップを開く。3千円、ばちを持参。大西さんTEL078・707・2293