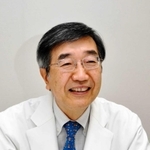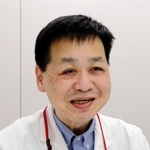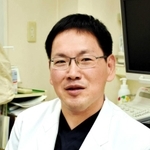いま、慢性腎臓病の患者さんが増え続けています。その数は1千万人以上とされ、末期となって人工透析を導入する人も31万人に達しています。慢性腎臓病は「国民病」といえるかもしれません。
近年の大きな特徴は、高齢者が多くかかること。健康長寿を阻む要因の一つになっています。かつての腎臓病は、比較的若い時期に免疫異常によって起こる慢性糸球体腎炎の患者が多かったのですが、1990年代以降、糖尿病、高血圧などの生活習慣病の増加に伴い、高齢で発症する人が増えました。
ですから、生活習慣病にならないようにすることが、慢性腎臓病の予防になります。検診で高血圧や糖尿病などが疑われた場合は、医師に相談し、治療を始めましょう。また、生活習慣病の予防には、生活習慣の改善が必要です。
糖尿病がなぜ増えているかははっきり分かっていませんが、社会が便利になったために、昔と比べて人間のエネルギー消費が少なくなったことが関係していると思います。つまり、運動量が減ったということです。
現代人は長く歩かなくても車や電車で移動できますし、掃除・洗濯にしても家電が発達して人の作業量が減りました。昔は珍しかった駅のエスカレーターも、いまは当たり前になりました。運動量を取り戻すには、意識して体を動かすしかありません。
また、高カロリーの食物が簡単に食べられるようになったのも、生活習慣病や肥満の増加につながっています。高血圧は塩分の摂取量が関わっています。日本人は1日平均10グラム以上の塩分を取っていますが、高血圧予防には1日6グラム以下が推奨されています。
高齢になってから人工透析を始めるのは負担が大きく、生活の質も低下させます。意識して体を動かし、食習慣を改善することで生活習慣病を防ぎ、ひいては慢性腎臓病を予防しましょう。(聞き手・森本尚樹、協力・兵庫県予防医学協会)
【にし・しんいち】1957年生まれ。新潟大学医学部卒。同大学准教授をへて、2012年から神戸大学大学院医学研究科教授。神戸市在住。
慢性腎臓病
腎機能の低下やタンパク尿、血尿などの異常の総称で、患者は日本の人口の13%に達すると推計される。末期には腎臓に代わって血液をろ過する人工透析あるいは腎移植が必要になる。