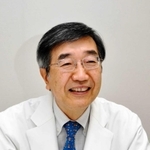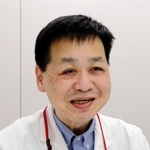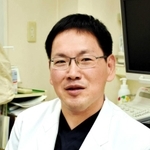今までなら平気だった坂道で息が切れることはありませんか。あるいは同世代と一緒に歩いていて、遅れてしまうことはありませんか。そのような場合、少し「貧血」に注意が必要かもしれません。
貧血とは、赤血球やそれに含まれるヘモグロビンが不足した状態を指します。ヘモグロビンは生命の維持に不可欠な酸素を肺から受け取り、全身に運ぶ役割を果たしています。血管が「高速道路」だとしたら、ヘモグロビンは酸素を積んで走る「トラック」です。この数が減ると、息切れや動悸(どうき)、倦怠(けんたい)感が出ます。
同じ貧血でも、高齢者と月経のある女性とでは事情が異なります。月経のある女性の貧血は、ヘモグロビンの材料となる鉄分が出血により不足することが原因です。この場合、鉄分を多く含む食材や鉄剤で補うのが有効です。一方、高齢者の貧血でまず必要なのは、鉄分の補給ではありません。かかりつけの内科を受診することです。なぜなら、別の病気が隠れている恐れがあるからです。
例えば胃や大腸など消化器系のがんです。これに伴う出血が貧血の原因になっている場合があります。ほかにも関節リウマチといった慢性炎症や、結核などの慢性感染症があると、ヘモグロビンを作るのに必要な鉄やホルモンの働きが低下します。別の病気に起因するこうした貧血を「二次性貧血」と呼びます。
気をつけてほしいのが、ヘモグロビンが徐々に減った場合、一定のラインを下回るまでは人間に備わった代償機能が働くため、症状が出にくいという点です。早期発見には健康診断で定期的に血液検査を受けることが大切です。
もう一つ、高齢者で増えているのが「骨髄異形成症候群」による貧血です。これは、赤血球を作る源となる骨髄細胞の遺伝子に傷が入り、血液ができなくなる病気です。残念ながら、傷が入る理由はまだ解明されていません。
ただ、近年はゲノム(全遺伝情報)を容易に見ることができる検査機器「次世代シーケンサー」が発達し、研究レベルでの活用が進んでいます。大量のデータを瞬時に解析するIT技術も進歩してきました。これらを融合させれば、遺伝子変異の原因や予防法が見つかる可能性は十分あります。今後は市民参加型の臨床研究も増えていくと思われます。機会があれば、参加してみてはいかがでしょうか。(聞き手・田中陽一、協力・兵庫県予防医学協会)
【まつおか・ひろし】1963年、北海道釧路市生まれ。神戸大大学院医学研究科修了。専門は血液内科学、血液腫瘍学。和歌山県立医科大などを経て、2009年から現職。日本造血細胞移植学会評議員や日本骨髄バンクの移植調整医師も務める。
松岡さんが勧める三つの作法
一、息切れや体のだるさがあれば、臆せず内科の受診を
一、軽度の貧血は症状が出にくい。定期的に血液検査を
一、病名を正しく知ることが健康維持の入り口
貧血の目安
血液に含まれるヘモグロビンの量は、男性なら0.1リットル当たり13~14グラム、女性なら12グラム以上が正常とされる。これを下回ると一般的に貧血とされるが、徐々に下がった場合、7~8グラムを切るまでは具体的な症状が出にくい。