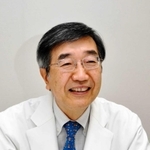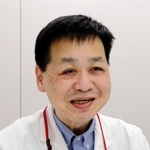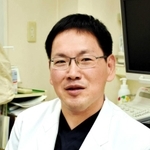見えることは、人生の楽しみにつながります。
人間は外部の情報のうち、約80%を視覚から得ており、目の健康は長寿を満喫するために欠かせません。
眼病のうち、初期の自覚症状がほとんどなく、発見が遅れがちなものがあり、定期的な眼科受診をお勧めします。その代表格が、糖尿病網膜症と緑内障です。
糖尿病網膜症は、糖尿病を発症してから5~10年で出てくることが多いのですが、一人一人の発症時期はさまざまで、目に異常がなくても安心してはいけません。
糖尿病によって、網膜に栄養を送る毛細血管が詰まると、栄養供給ルートを確保しようと、新しく「新生血管」ができます。この新生血管が破裂して目の中へ出血すると、血液にはのりのようになる成分が含まれており、網膜の表面に膜が張ってしまいます。膜が収縮する時に網膜をはがしてしまうのです。最悪の場合、失明に至ります。
手遅れにならないためには画像検査が必須ですが、嫌がる人が多いのも事実です。目薬で瞳孔を開くので検査直後は運転できない上、カメラが撮影できる範囲が限られているため、眼球を動かして何度もまぶしい撮影をしなければなりません。それでも最近は、瞳孔を開かずに1回撮影するだけで済む超広角カメラが普及するなど、検査の環境が向上しつつあります。
言うまでもなく、糖尿病の治療や生活改善が最も肝心です。食事の量を抑えて血糖をコントロールしながら、適度な運動を心掛けてください。
また、同じく自覚症状の少ない緑内障も、早期発見が重要です。特に新生血管が原因のものは視力を失うことがあります。今は最新鋭の機械で網膜の厚みを測定し、症状があるかどうかを短時間で判断できます。
片目だけが進行する病気にも、注意すべきです。例としては、視界がゆがんだり、中心が見えなくなったりする「加齢黄斑変性」が挙げられます。両目を開けていると、片方が悪くなっても、良い方の目がカバーし、異常に気付きにくいものです。片方ずつ見え方をチェックする習慣をつけてはどうでしょうか。
その他、加齢に伴う目の異変は多岐にわたります。白内障で活動性が低下し、認知症が疑われた人が、手術で視力を回復し、元気になったケースもあります。「年のせい」とあきらめず、気になることがあれば眼科で相談し、心配を解消してください。(聞き手・佐藤健介、協力・兵庫県予防医学協会)
【いしだ・かずひろ】1962年、大阪市出身。京都大医学部卒。米ハーバード大スケペンス眼研究所留学。神戸市立医療センター中央市民病院、神戸アイセンター病院を経て、2018年4月から現職。同市東灘区在住。
石田さんが勧める三つの作法
一、自覚症状がなくても早期発見のために定期受診する
一、片目ずつ見え方をチェックする習慣をつける
一、気になることがあれば眼科で相談する
糖尿病網膜症
糖尿病の代表的な合併症で、初期には自覚症状はないが、進行すると視野が狭くなり、さらに悪化すると失明の危険性もある。高血糖により、網膜に張り巡らされた細かい血管が傷んだり、詰まったりすることが原因で起きる。