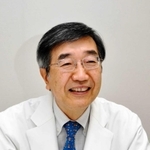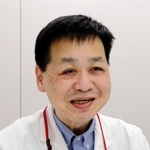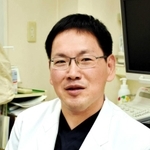年齢を重ねる中で、けんしょう炎や軟骨の摩耗による手の関節痛に悩まされ、病院を訪れる人は多いです。治療や手術などで炎症を鎮めることはできますが、痛みを伴う生活には精神的な負担もあり、生活の質を低下させることにもつながりかねません。
人間の指は屈筋腱(けん)によって曲げ伸ばしができます。屈筋腱の浮き上がりを押さえる部分を靱帯(じんたい)性けんしょうといい、トンネル状に腱を包みます。けんしょう炎は曲げ伸ばしをした際、腱と靱帯性けんしょうが擦れ、炎症を起こすことで痛みが発生します。
治療には湿布などを貼って安静にするほか、局所麻酔入りステロイド注射をけんしょう内に注入し、症状を抑える方法があります。注射を3~5回ほどして治らないようなら、手術でけんしょうの一部を切り、腱とけんしょうの摩擦を無くすことで痛みを取り除きます。
けんしょう炎の原因は指の使い過ぎのほか、加齢で腱がけば立ち、腱とけんしょうの摩擦が大きくなることもあります。長い時間、編み物などの手を使う作業を続けない▽重い物を持たない-など、負担となる動作を控えるよう意識することも大切ですが、腱の滑りをよくすることも重要です。そのため、次のような予防法を実践してみましょう。
お風呂の中でゆっくりと指を広げて握ります。靱帯性けんしょうの内側には滑膜性けんしょうがあり、腱の滑りをよくする滑液を出します。グー、パーと握ったり開いたりすることで、滑液を腱に浸透させましょう。
回数は10回ほどで構いません。大切なのはしっかり指を伸ばし、ぐっと縮めることです。お風呂で温めることで血液の循環がよくなり、筋肉を柔らかくする効果もあります。
また、ゆっくりと指を動かすことで、腱やけんしょうが腫れて動かしにくくなる変化にも気付きやすくなります。症状が軽い状態で発見すると、治るのも早くなるので異変を感じたらすぐに診てもらうようにしましょう。
けんしょう炎は更年期や出産期の女性に多いといわれます。滑膜の減少には、女性ホルモンの変動との関係を指摘する研究もあります。
けんしょう炎をきっかけに寝たきりになるなど、生活が変わることはありません。しかし、手を動かすことは認知症の予防にもつながるため、十分に気を付けましょう。(聞き手・篠原拓真、協力・兵庫県予防医学協会)
【やまさき・きょうこ】1954年、神戸市生まれ。神戸大医学部卒。同大学院博士課程修了。神戸大医学部付属病院や神戸労災病院などを経て、2010年から三菱神戸病院整形外科部長。16年の定年退職後も同病院で医師として勤務する。
山崎さんが勧める三つの作法
一、手の使い過ぎに注意する
一、指の運動で腱に滑液を浸透させる
一、ゆっくり指を動かし、症状をチェック
けんしょう炎の種類
腫れた腱がけんしょうに引っ掛かり、指の曲げ伸ばしがしにくくなるばね指や、親指を動かす2本の腱とけんしょうが炎症を起こし、手首の親指側に痛みが出るドケルバン病などがある。