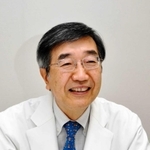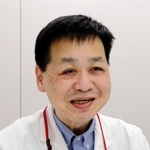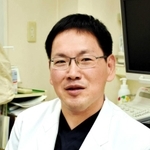長生きをするためにはこの食べ物が良いと、よくテレビなどで取り上げられますが、特定の食べ物を食べることで健康になることはありません。大切なのはバランスよく食事をし、楽しんで食べるという当たり前のことです。
国が提唱している「食事バランスガイド」というものがあり、1日に何を、どれだけ食べればいいか、目安を示しています。食事を考える上で、とても参考になります。しかし、中には目安に合うよう「十分な食事を毎回そろえなければ」と頭を悩ます人もいるかもしれません。
もっとシンプルに考え、「主食、主菜、副菜」を1食ごとに意識すれば、自然とバランスの良い食事になります。少量でも構わないので、まずは1食にこの三つをそろえて食事をすることを意識してみましょう。
そういった点で見ると、日本の伝統的な食事「和食」というのは主食、主菜、副菜が基本となっているため、理にかなっていると思います。
ただ、一点だけ気を付けなければいけないのは、煮物や汁物は、塩分が多くなりやすいということです。塩分の取り過ぎには注意しましょう。
健康長寿の基本となる食事ですが、ただ栄養を取ればいいというのではありません。食事を通したコミュニケーションも重要です。おいしく楽しんで食べることは食事を豊かにします。
今、若い人の中には糖質オフダイエットとして、炭水化物を取らないようにするなど、バランスの良い食事を取る習慣が身についていないように思えます。例えば、お孫さんに料理の仕方を教えながら調理し、いっしょに食卓を囲むのもいいのではないでしょうか。
以前、調査で80代の女性に昔の料理の作り方を聞いた時、調理の仕方を話すだけで生き生きし、世話をしている介護士さんが「こんなにしっかりしゃべるのは初めて見た」と驚いたということがありました。
作り方を思い出すことや調理方法を伝えるということは、記憶を呼び戻して頭もしっかりし、認知症予防にもつながるのではないでしょうか。楽しんで食べることで消化吸収率が良くなるというデータもあります。
健康長寿のために楽しんでバランスの良い食事をすることを心掛け、日本の伝統的な食事文化を若い人にも伝えてあげてください。
(聞き手・篠原拓真、協力・兵庫県予防医学協会)
【さかもと・かおる】1961年、福岡市生まれ。86年に奈良女子大大学院、2008年に神戸大大学院総合人間科学研究科を修了。専門は調理方法などを研究する調理科学。賢明女子学院短大教授などを経て、15年4月から現職。
坂本さんが勧める三つの作法
一、1食ごとに主食、主菜、副菜を意識して
一、食事を通したコミュニケーションを大切に
一、穀物や野菜、肉、魚と何でも食べよう
食事バランスガイド
健康を維持する食生活の目安として、厚生労働省と農林水産省が2005年に提言した。料理を主食や副菜、果物など五つのグループに分け、1日に取るべき適切な量や組み合わせを、こま状の絵を用いて示している。