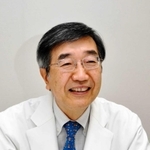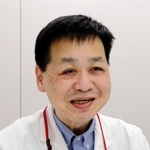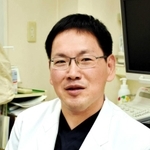人体に重要な役割を果たしながら、異常を見過ごすと健康を脅かすかもしれない臓器の一つ、それが「胆道」です。
肝臓で作られて食べ物の消化を助ける胆汁を一時的にためる「胆のう」と、胆汁が十二指腸に運ばれる経路「胆管」を指します。
そこががんになっても、自覚症状がほとんどないため、早期発見が非常に難しく、死亡率も高いのです。
胆汁の成分が結晶になることなどで「胆石」が形成されます。胆石は炎症などを引き起こす「胆石症」の原因となり、がん化の危険因子としても指摘されています。予防と適切な治療が、長寿には欠かせません。
日本人のおよそ5%が、胆のうに胆石を持っているとされており、決して珍しくはありません。そのうち、症状が実際に現れるのは半分ほどで、腹部や背中の鈍痛、発熱、吐き気のほか、重症化すると黄疸(おうだん)にも悩まされます。
胆石症は、細菌感染などが原因となるケースもありますが、大半はコレステロールの結晶化によるものです。特に若い世代でコレステロール由来の胆石の比率が高くなります。肥満は大敵です。
適度な運動はもちろん、とりわけ気を配るべきなのは食事です。脂質やアルコールをなるべく避けてください。脂っこくて刺激のある物を食べ過ぎると、消化に必要な胆汁を押し出すために胆のうの収縮が強く促されます。そうなると、胆のう内の胆石が移動し、十二指腸につながる胆管などに流れることがあります。
胆石が詰まると「急性胆のう炎」や「急性膵炎(すいえん)」といった合併症で死に至る危険性もあります。さらに、胆石を持つ人の胆のうがんの危険率は、持たない人の約35倍に上る-との報告もあります。
みぞおちやおなかの右側が痛み続けるようなら、超音波検査をお勧めします。胆石の有無を簡単に確認できるので、人間ドックなどの機会を利用してください。
治療には、胆石を溶かす薬や、衝撃波で胆石を割る手法がありますが、全てを取り除けないので再発リスクが伴います。だから、胆のうの摘出手術が第一選択です。胆のうが失われても人体にほぼ影響はありません。今は腹部を切り開かず、小さな穴から器具を挿入する腹腔(ふくくう)鏡手術が普及しています。
体に負担の少ない治療法が確立されている今、健康的な生活習慣を続けつつ、早期発見に努めてください。(聞き手・佐藤健介、協力・兵庫県予防医学協会)
【あじき・てつお】1963年、兵庫県太子町生まれ。神戸大医学部を経て、同大病院消化器外科などで勤務。専門は胆道疾患で、肝臓や膵臓(すいぞう)の分野にも精通し、同大学院医学研究科肝胆膵外科学特命教授などを歴任。2017年4月から現職。
味木さんが勧める三つの作法
一、脂質の多い食事を控え、肥満を避ける
一、健康診断や超音波検査で早期発見に努める
一、腹痛などの症状が出れば、手術などで治療する
胆石症
肝臓から出て消化を助ける「胆汁」のコレステロールが結晶化するなどして胆石となり、激しい腹痛を起こす。多くは胆汁をためる「胆のう」にでき、胆汁を十二指腸に運ぶ「胆管」や、肝臓内に生じることもある。胆道がんとの関連も指摘される。