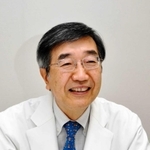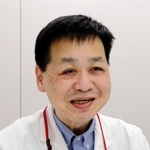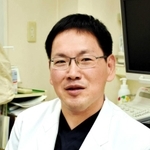「栄養のバランスがあまり取れていない」
「運動が不足している」
「お酒を控えめにしたほうがいい」
「少し太りすぎではないか」
病気と真剣に向き合う医師が良かれと思って掛けた言葉に対しても、患者個人がしばしば戸惑いを感じてしまう面があったのが、昔ながらの予防医学でした。
確かに間違っていません。ただ、そもそも体の状態は、自分で客観的に把握しにくいもの。医師のアドバイスだけでは、何をどう改善すればいいのか手探りに陥ったり、実際に改善に取り組んだとしても、いまひとつ達成感を得られなかったりすることもあります。
そこで鍵になってくるのが、インターネットです。体の状態を可視化し、健康になるプロセスを楽しめる工夫が可能になります。歩数や睡眠の質を測定できるスマートフォンアプリも普及しており、効果的に活用することをお勧めします。
とりわけ、紹介したいのが「PHR」です。個人の健康に関する情報をデータ化して一元管理し、生活改善につなげる取り組みで、日本で広まりつつあります。神戸市も、市民登録制の「市民PHRシステム(MY CONDITION KOBE)」を開発し、今春には専用アプリが無料で利用できるようになります。
このアプリでは例えば、ある市民の特定健診の結果を基に、当人に適したアドバイスを、スマホを介して受けられます。また、「1日1万歩」「食事メニューをスマホに入力」といった、健康を増進させる行動を取れば、商品割引などの特典が得られる健康ポイントも貯められます。
健康づくりに向けたアドバイスを日常に取り入れるポイントとしては、頑張り過ぎないこと。少しの運動でも病気の予防や筋力低下を食い止める、という研究成果はたくさん発表されています。無理なく続けることが最も大切で、アプリやインターネットで健康づくりを楽しむこともその一助になります。
インターネットに慣れていない高齢者にもアドバイスです。人とのつながりを積極的に持ってください。健康に関する行事の情報も入るでしょうし、スマホの扱いにたけた方とも出会えるかもしれません。アンテナを立てておくことが、健康長寿のために重要なのです。
(聞き手・佐藤健介、協力・兵庫県予防医学協会)
【みき・りゅうすけ】1977年、和歌山市生まれ。九州大医学部卒。救急、循環器、公衆衛生、疫学などが専門。兵庫県災害医療センター救急部副部長などを歴任。京都大大学院で健康と社会の関係性を研究。2018年4月から現職。
三木さんが勧める三つの作法
一、頑張り過ぎない範囲で、軽めの運動を続ける
一、人とつながり、健康づくりへのアンテナを張る
一、インターネットも利用し、自らの状態をチェック
PHR(PersonalHealthRecord)
心身の状態や受診歴に関する個人情報を自ら電子保存し、必要に応じて提供するシステム。医療・介護施設が連携した患者対応や、行政の生活指導など多目的を想定。匿名化したデータを研究や産業に生かすことも期待される。