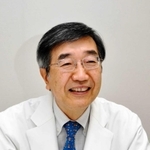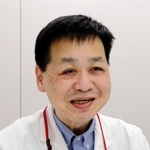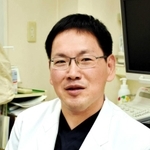脳の血管が詰まったり破れたりして起きる脳卒中は、半身のまひや言語障害を引き起こすため、健康長寿を考える上では予防が重要です。しかし、発症した場合でも近年は治療やリハビリテーションが大きく進化していますので、あきらめずに立ち向かうことが大切です。
脳卒中の危険因子には加齢や高血圧、糖尿病、高コレステロール、喫煙、過量の飲酒がありますが、特に怖いのが高血圧。予防には血圧のチェックが不可欠です。健康診断で血圧を測るだけでは、朝だけ血圧が高いといった異常を見逃す恐れがありますので、日ごろから家庭で測っておく必要があります。血圧の上限は上が130、下が85ぐらい。それより高い場合はかかりつけの医師に相談してください。
脳卒中の前兆症状として、典型的なのは片方の手足が動かしにくくなること。ほかにも、ろれつが回りにくい、視野が狭くなる、などがありますが、痛みはないので大したことないと思いがちです。気になる症状があれば、すぐに専門の医療機関に診てもらってください。
脳卒中は、早期に治療を始めるかどうかで、その後の生活の質が大きく変わります。動脈が詰まる「脳梗塞」には、t-PAという血栓を溶かす薬や、血管にカテーテルを入れて詰まりを治す方法が開発されましたが、早く治療しないと効果は見込めません。
神経リハビリなども格段に進歩しています。かつては入院直後の患者さんは安静にさせていましたが、リハビリは早く始めるほど効果が高いことが分かってきました。重症の方も治療と並行してリハビリを始め、日常生活を送れるまで回復しています。
脳卒中になると、患者さんも家族も落ち込みがち。気持ちの切り替えが大切です。リハビリで在宅復帰した後に再発する人も多いので、減塩食に切り替えるなど生活改善に取り組みましょう。(聞き手・田中伸明、協力・兵庫県予防医学協会)
【よしだ・やすひさ】1961年生まれ。神戸大学大学院医学研究科修了。同大学病院脳神経外科助手などを経て、95年に吉田病院入り。2009年院長。神戸市東灘区出身・在住。
神経リハビリ
脳卒中などにより破壊された神経回路を再生させ、まひした機能を回復させるリハビリテーション。兵庫医科大の「CI療法」、吉田病院などが行う「川平法」などが知られている。