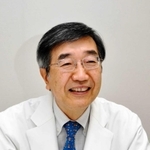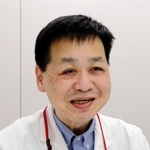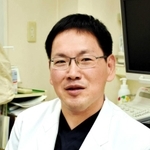最近、独り暮らしの女性を中心に、自分は認知症ではないかとすごく心配して受診される方が増えています。予約の日時を忘れず、1人で病院に来られる時点で認知症の定義からは外れるのですが、検査した上で根拠を説明し、安心してもらっています。
認知症とは、脳の萎縮や脳細胞の壊死(えし)で記憶や認識機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態です。約束のすっぽかしが増えたり、預金が引き出せなくなったりしたら、認知症の可能性があります。
さらに最近問題になっているのは、徘徊(はいかい)したり、暴力的になったりする周辺症状(BPSD)です。迷ったあげく鉄道事故に遭うなどして迷惑をかけるのでは、と心配になるのは無理もないことです。
高齢になってから発症する認知症は、悪い生活習慣が引き起こす糖尿病や高血圧が大きな危険因子です。逆に言うと、認知症を意識しなくても、生活習慣病にならないよう心掛ければ予防につながるのです。心配しすぎによるストレスも脳の健康にはよくありません。
認知症予防として脳を鍛える脳トレが注目されていますが、特別なことをしなくても、読書でも絵を描くのでもいいので趣味を楽しむのがお勧めです。脳が活性化しますし、楽しいなどの感情を伴う記憶はなかなか忘れません。
物忘れをなくす薬はまだありませんが、認知症の症状を和らげる薬が開発され、患者さんの状態に応じて使い分けています。脳に「老人斑」という有害物質がたまらないようにして認知症を予防する薬の実験も始まっています。
認知症予防でもう一つ大事なのは、家族や近所の人と仲良くしておくことです。人間関係が良好だと、少々日常生活に支障があっても助けてくれますし、もし認知症になっても精神的に安定し、周辺症状が少なくなります。今のうちに、周囲の人と積極的に会話してみませんか。(聞き手・田中伸明、協力・兵庫県予防医学協会)
【こわ・ひさとも】1970年、東京都生まれ。東京大学大学院修了。同大学病院で認知症専門外来を立ち上げ、2010年から神戸大に。認知症専門医。芦屋市在住。
主な認知症の種類
認知症のうち半数以上を占めるのがアルツハイマー型で、男性より女性が多い。次いで脳の血管障害で起きる脳血管性、男性に多いレビー小体型、若い人も発症する前頭側頭型がある。