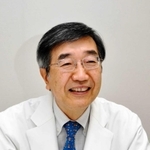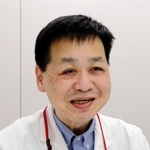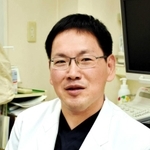臨床検査技師である私は、機械で測る検査をしますが、それだけではありません。これまで、顕微鏡で細胞を見てがんかどうか判断する「細胞診」と言う分野に長く携わってきました。客観的な数値ではなく、文字による主観的な報告のため、経験や知識の蓄積が特に重要な仕事です。
正常な細胞が何らかの原因により、無秩序にどんどん増えてしまう状態がいわゆる「がん」です。正常な細胞は同じような顔つきできれいに並び、規則性がありますが、異常が起こると大きさや形に差が出てきます。明らかにおかしくなくても、放置すると危ない「前がん細胞」も存在します。また、細胞も人間と同じで、悪人顔をした善人や、善人顔をした悪人がいます。
私たちの仕事は、医師の診断に先立ち、経験と知識によってこれらの細胞をふるい分けることです。がんは早く見つければ治る病気になってきたので、早期発見が非常に大切です。
細胞診は、人間ドックや市町村で行われる子宮頸(けい)がんや肺がんの検診などで行われます。こすり取った細胞やたんに含まれる細胞を用いるので、体への負担が少なくてすみます。自覚症状がなくても定期的に受けましょう。
検診以外では、病院で行われる尿検査も重要です。尿には体内からはがれた細胞が含まれるため、自覚症状がなくても膀胱(ぼうこう)がんなどが見つかることがあります。肝臓や胆のう、膵臓(すいぞう)のがんなどが疑われた場合、直接針を刺して細胞を採取することもあります。
最近は、細胞の核に含まれる遺伝子の解析が進み、長寿遺伝子「サーチュイン遺伝子」が注目されるようになりました。規則正しい生活や「腹八分目」を心掛けると活性化すると言われます。また、ポリフェノールの一種「レスベラトロール」もこの遺伝子に対し、同じ作用を起こすとされています。お酒を飲むなら赤ワインがお勧めです。
細胞診ではありませんが、採血も臨床検査技師の仕事の一つです。血管は年を取るとだんだん弾力を失うのですが、農業や漁業に携わっている人は都会の人に比べて血管が若々しく感じます。健康を保つには、普段から体を動かすことが大切だと採血業務から教えられている気がします。(聞き手・森 信弘、協力・兵庫県予防医学協会)
【さなだ・こういち】1961年、愛知県一宮市生まれ。国際医学総合技術学院(現・岐阜医療科学大)卒。兵庫県立西宮病院などを経て2016年から現職。日本臨床細胞学会認定の細胞検査士。神戸市中央区在住。
真田さんが勧める三つの作法
一、自覚症状がなくても定期的に人間ドックや検診を
一、規則正しい生活や「腹八分目」で長寿遺伝子活性化
一、体を動かして血管の老化防止
臨床検査技師
医師の指示で検査を行う国家資格。血液や尿など人から採った材料を機械で測る「検体検査」、心電図などで患者から直接情報を集める「生体検査」のほか、顕微鏡で細胞を観察する「形態検査」がある。