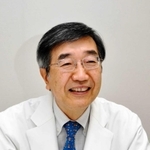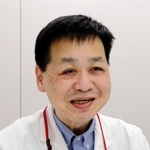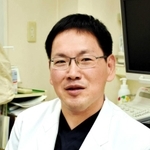超高齢社会を迎えた今、多くの人が直面する生命の危険因子として動脈硬化が挙げられます。動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞を起こし、命を落とすことにつながります。高血圧や脂質代謝異常、糖尿病、喫煙などが原因となりますが、加齢が最大のリスクで、誰もその魔の手からは逃れられません。
テレビ番組でも、突然の発作で胸を押さえるシーンを目にすることがあると思います。走ったり、坂を上ったりするたびに繰り返し起こる胸への圧迫感は、労作性狭心症の可能性があります。じっとしていると少しずつ治まり、5分ほどで改善しますが、油断は大敵です。
心臓の血管、冠動脈の詰まりは、健康診断ではほぼ見つかりません。冠動脈は内径の9割が詰まって初めて自覚症状が現れます。発作の回数や痛みの強さが増したり、痛みがなかなか治まらなくなったりするのはとても危険なサインです。胸の痛みはあらゆる臓器が原因で起きますが、心臓の異常であれば、すぐに治療が必要な場合があるので、直ちに医師に相談してください。
検査技術の進歩で、緊急治療の必要がなければ、すぐに体内にカテーテル(医療用の管)を入れなくてもよくなりました。冠動脈のコンピューター断層撮影(CT)検査で、血管の状態を見られます。心筋への血流量を確認する「心臓核医学検査」で、血管が狭いことによる心臓への影響を調べることもできます。
これらの検査で狭心症が疑われれば、入院してカテーテルでの検査、治療を行います。狭心症であれば入院期間は1週間程度です。かつてカテーテルは、太ももの付け根や肘の血管から入れていたため、施術後に数時間、脚や肘を固定する必要がありました。今では多くの場合、手首の血管から挿入し、終わればバンドを着けるだけで、すぐに歩くこともできます。血流が滞った冠動脈に固定するステント(細長い筒状の金属製の網)も進化し、血管が再び狭まるリスクが大きく低下しています。検査、治療を受ける患者さんの負担はとても少なくなっています。
こうした危機を先送りする何よりの予防法は、禁煙し、運動を習慣づけることです。薬の処方があれば指示通りに使い続け、食生活で塩分やカロリーを過度に摂取しないよう心掛けることが大切です。(聞き手・山路 進、協力・兵庫県予防医学協会)
【たかや・ともふみ】1973年姫路市生まれ。神戸大医学部卒、同大学院博士課程修了。同大助教などを経て、同大学院客員准教授。2016年4月から現職。日本心血管インターベンション学会専門医。加古川市在住。
高谷さんが勧める三つの作法
一、たばこを吸うのは、きっぱりとやめる
一、日頃から歩くことを心掛け、習慣づける
一、処方された薬は指示通りに続ける
冠動脈のカテーテル治療
手首などに太さ数ミリの筒状の針を刺し、長さ約1メートルのストロー状のカテーテルを心臓まで通す。その中にワイヤを差し入れ、冠動脈の狭まった部分で、風船を膨らませてステントを固定。血管を広げ、血流を改善させる。