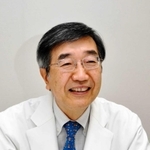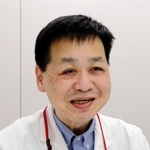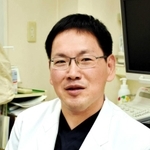作業療法士として高齢者のリハビリを担当する中で、体の運動とあわせて編み物やちぎり絵などの作業活動をよくやってもらいます。誰かにあげるために作品を作るのもいいかもしれません。自宅でも続けることで生きがいを持って生活することができます。
簡単で手軽にできる運動としては、よく散歩を勧めています。できれば複数の人と歩くのがいいですね。誰かと待ち合わせすれば、それが継続の動機になります。会話の内容など頭を使いながら体を動かすのは、認知症予防につながるという報告があります。
いろいろなコースを歩くのも脳への刺激になります。つえや押し車は積極的に使っても構いません。犬を飼っている人同士で毎日歩いている人も多くいます。散歩によって近所のつながりができることもあるでしょう。
自分で活動を継続するのが難しい人は、デイサービスの施設や地域のふれあい喫茶などを見つけ、積極的に出掛けるのが大事だと思います。最近のデイサービスではリハビリをよくやっています。利用者同士でしゃべると自分と同じ病気の人がいて、いろんな情報が入る利点もあります。
デイサービスの利用に抵抗を感じるのは、やはり男性が多いですね。でも、一度行ってみると、思ったほど嫌でなくなることが多いようです。自分から人の輪に入るのが苦手な人も、最初は「運動しよう」と思って一歩を踏み出せばいいと思います。
施設では機械などを使った運動にも取り組んでいて、筋力低下防止などの効果を得られます。ただ、施設に通う意義は、外出やさまざまな人と話すことも大きいですね。
本当は歩けるだけの能力はあるのに、車いすに乗っている人も少なくありません。でも何かのきっかけで認識が変われば、急激に変化が表れることもあります。90歳くらいの男性で、出会ったときは車いすに乗っていたのに、盆踊りに参加できるまで元気になった人もいました。施設で職員と会話するのが楽しくて生活にやる気がでたようです。
介護保険にも訪問サービスがありますが、施設に通えば生活のリズムができるし、スケジュールを管理しようという気持ちにもなります。リハビリではあまり細かいことは言わないようにしています。無理をすると長続きしません。短い距離の散歩でも、続けることが長期的にはいいと思います。(聞き手・森 信弘、協力・兵庫県予防医学協会)
【かじた・ひろゆき】1975年、神戸市長田区生まれ。神戸大大学院修士課程(保健学)を修了。デイケア施設での勤務を経て、2006年から現職。作業療法士。同市西区在住。
梶田さんが勧める三つの作法
一、無理なくできて興味の持てる活動を続ける
一、会話しながら散歩をして認知症予防
一、デイサービスなどの施設を有効に活用
作業療法士
リハビリテーションの専門家に与えられる国家資格。医療や福祉、介護の現場で、病気やけが、障害がある人を支援する。掃除や調理をはじめ、手芸や運動、勉強など日常生活のさまざまな活動を通して援助する。