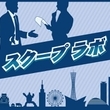これまで貸借対照表と損益計算書、キャッシュフロー計算書を見てきました。今回は貸借対照表と損益計算書の活用ポイントを、もう少しご紹介しましょう。
まず貸借対照表です。貸借対照表に記載された純資産(自己資本)が、負債と純資産の合計に占める比率を自己資本比率と呼ぶことは、既に触れました。大まかにいえば、どの程度借金に頼らない経営ができているかを示す数字で、経営の健全性の判断に使われます。
この数字が高いほど、財務的に安定しているということになります。50~60%程度ならば優良とされ、少なくとも30%程度は確保したい水準と考えられているようですが、業種などによってかなりばらつきがあります。
有利子負債の増減も見逃せません。有利子負債は文字通り、利子を付けて返済する必要のあるお金で銀行などからの借入金や社債が代表的です。有利子負債が増えるほど、支払わないといけない利息も増えるので、経営の先行きを見極める上で重要なチェック項目です。
次に損益計算書です。この書類で注目したいのは売上高総利益率です。売上高から仕入れの費用など(売上原価)を引いた数字(売上総利益)が、売上高全体のどれだけあるかを示します。
売上高総利益率の数字が大きいほど、収益性が高い魅力のある商品を持っていると判断できるとされているようです。この数字も、平均的な水準が業種によって大きく異なるので、同業他社との業績比較などに生かされることが多いようです。
ほかにも、経営状態を判断するのに利用される数字があります。ただ、足元の数字ばかりに目を向けることは、よくありません。
例えば今は魅力的な商品が多く売上高総利益率が高い企業も、これからどうなるか数字だけでは予測できないのです。多角的な視点を欠かさないよう心掛けましょう。